出典書籍
西暦1107年 宋時代 『和剤局方』 by陳思文 太平恵民和剤局方(たいへいけいみんわざいきょくほう)ともいう。宋・太医川編。1078~1085年に刊行。宋代の薬局法ともいうべき書で、ちなみに日本の薬局方の名はこの書より起ったものである。現存するものは10巻で諸風、傷寒など14門、788方に分類される。処方毎に主治、配伍、修制法などが記されており、広く流布し、影響の比較的大きい書である。→処方使用期間:910年間

【適応症】産後あるいは流産後の疲労回復、無月経、希少月経、月経不順、冷え症、しもやけ、しみ、血の道症、高血圧症、貧血症、更年期障害、過多月経、産前産後の諸種の障害、乾燥性の皮膚病、下肢運動麻痺、カリエス、産後の舌ただれ、産後の脚弱、腎炎、子宮出血、進行性指掌角化症


次の症状のいくつかある方は、四物湯が良く効く可能性が大きいです。
●血虚(貧血)に対する代表的基本処方です。血の不足による栄養不良状態が全身に現れたもので、顔や髪に艶がなく、爪がもろい、皮膚のかさつき、疲労脱力感、筋肉のききつれ、イライラ、めまいなどの症状を伴う人に適します。
●シモツSは、顔や皮膚の色艶がわるい方に、また血の道症や生理不順などの症状のある方に用いる漢方の基本的な処方です。これらの症状は自律神経やホルモンのバランスとも関係があるとされていますが、漢方では「血虚」(けつきょ)のあらわれとみなし、それらを改善するのにシモツSが用いられます。
●また、しもやけ、しみ、指掌角皮症(主婦湿疹)にも効果があります。
●本剤は、漢方の古典「和剤局方」(わざいきょくほう)(宋代)収載の処方に基づいて作られたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。
●本方は4種類の生薬から成り、処方名はこれに由来します。
●滋養強壮生薬製剤。
西暦1107年 宋時代 『和剤局方』 by陳思文 太平恵民和剤局方(たいへいけいみんわざいきょくほう)ともいう。宋・太医川編。1078~1085年に刊行。宋代の薬局法ともいうべき書で、ちなみに日本の薬局方の名はこの書より起ったものである。現存するものは10巻で諸風、傷寒など14門、788方に分類される。処方毎に主治、配伍、修制法などが記されており、広く流布し、影響の比較的大きい書である。→処方使用期間:910年間
 皮膚が枯燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症:
皮膚が枯燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症:
産後あるいは流産後の疲労回復、月経不順、冷え症、しもやけ、しみ、血の道症。
※血の道とは、本来血液の通る血管のことで、月経時、更年期、産後などの女性に見られる頭痛、めまい、精神不安などの諸症状を血の道症といい、子宮関係の病気の俗称としても使われています。

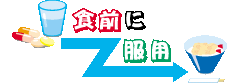 食前または食間に服用してください。
食前または食間に服用してください。
食間とは…食後2~3時間を指します。
年齢 1回量 1日服用回数
大人(15歳以上) 4錠 3回
15歳未満7歳以上 3錠 3回
7歳未満5歳以上 2錠 3回
5歳未満 服用しないでください
〈用法、用量に関連する注意〉
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

 使用上の注意
使用上の注意
相談すること
1.次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦または妊娠していると思われる人。
(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
(4)胃腸の弱い人。
(5)下痢しやすい人。
(6)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合
関係部位 症状
消化器 胃部不快感、食欲不振、腹痛
皮ふ 発疹・発赤、かゆみ
(2)1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合
3.次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください
下痢
【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
(4)水分が錠剤に付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
(5)湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。
【妊娠・授乳の注意】![]()
●妊婦または妊娠の可能性のある人は、使用できない場合があります。